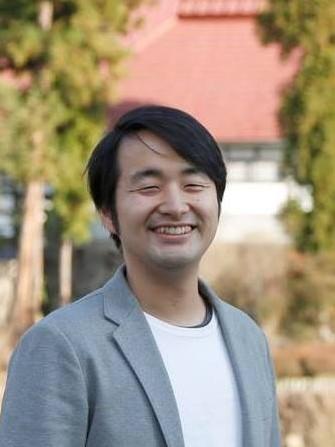【終了レポート】令和4年度 地方創生実践塾in長野県小布施町
終了レポート
2022年07月26日
「地域内外の人々が溶け合う小布施流まちづくり」~「協働と交流」で取り組む「環境先進都市」への挑戦~
令和4年5月27日(金)~28日(土)の2日間、長野県小布施町で、「地域内外の人々が溶け合う小布施流まちづくり」~「協働と交流」で取り組む「環境先進都市」への挑戦~をテーマとして、令和4年度地方創生実践塾を開催しました。全国各地の行政職員や大学生など27名にご参加いただきました。
■1日目:5月27日(金)
●オリエンテーション
講師:林 志洋 氏 (小布施町総合政策推進専門官) 会場:小布施町役場 講堂
小布施町の概要やまちづくりの歴史について紹介があった。
小布施町では1980年代から、「町並修景事業」が実施されてきた。高井鴻山記念館や小布施堂周辺の敷地を中心に、3個人・2事業者・行政の6者が発端となり、住む人・訪れる人が心地よく過ごせる町並み空間を形成してきた。「栗の小径」などは現在の小布施町を象徴する空間となっている。
特にこの事業では、保存ではなく修景、という意識が重要である点を強調していた。保存の場合、昔のモノを正解とするため不便もそのまま残すことになる。これに対し、修景の場合は昔ながらのエッセンスは残しつつ、住民目線で新たなまちづくりを行うこととなる。
この新たなまちづくりが、住民にとっても住みやすく、魅力あるまちづくりにつながっていくとの話があった。
また、小布施町は、修景の意識が共有され、地域住民の庭をオープンガーデンとして観光客等に開放するなど、町並や観光資源が地域住民等により作り上げられてきているとの説明があった。
さらに、近年の取組としては、小布施町をフィールドして地域課題の解決に取り組む若者による「小布施若者会議」が開催され、課題の解決だけではなく、まちの魅力を向上させる活動について話し合いを行っており、小布施町のまちづくりは、町並の整備(内部)から人的な交流(外部)へシフトし、新たな局面に進みつつあることを感じた。
●講義①
講師:桜井 昌季 氏 (小布施町長) 会場:小布施町役場 講堂
はじめに、「観光には、食べもの、見るもの、買うものが必要」との説明があった。
これは、町並み保存地区(見るもの)は全国に数多く存在するが、まちを周遊してもらうためには「食べもの」と「買うもの」が必要であり、その視点を持って小布施町が発展するよう取り組んでいる、ということであった。
「修景事業は、行政からではなく、地域住民からスタートした」「小布施町は歴史が浅く、守るのではなく使う・遊ぶという視点が大事」「整った保存整備は訪れた人が飽きてしまうが、小布施町の修景整備は整いすぎないところが飽きさせない」などの複数のキーワードで説明があり、これまでの小布施町の取組の考え方、歴史などについて説明があった。
また、今後の小布施町のビジョンとして「小布施町を現在の湯治場に」をコンセプトに、交流と協働のまちへ発展させたいと語った。
●まちあるき
【行き先:中心部の「町並み修景事業」の実施地域】
フィールドワークでは、3グループに分かれ、小布施町中心部の「町並修景事業」の実施地域を歩き、保存ではなく修景のまちづくりを見学した。
「(建物)外はみんなのもの、(建物)内は自分たちのもの」という考え方を、地域住民や地元の事業者が共有し、自らの敷地を誰もが通って楽しむことができるオープンガーデンが作られていた。修景事業の実施地域は面積としては広くないものの、このオープンガーデンにより、まちを周遊する楽しさが生み出されている。
実際にまちを歩いていると行き止まりがなく、まちを周遊して楽しめるとともに、修景事業を地域住民等が始めたことが、小布施町の修景事業を中心としたまちづくりに寄与していることを、現場から感じとることができた。
●パネルディスカッション①「地域内外の人々が溶け合う小布施流まちづくり」
パネリスト
林 志洋 氏 小布施町総合政策推進専門官
塩澤 耕平 氏 (一社)ハウスホクサイ代表理事
日高 健 氏 (一社)小布施まちイノベーションHUB理事
遠山 宏樹 氏 (一社)小布施まちイノベーションHUB
会場:ハウスホクサイ
初日の最後は、小布施町に移住した若者により、小布施町の良いところ・苦労したところをメインとした、パネルディスカッションが行われた。
パネラーからは「やりたいことができるまちに人は集まる」という考えが示されたが、実際に、小布施町では役場からのサポートとして、移住者と地域住民との橋渡しがしっかり行われていたほか、住民自身も積極的にかかわって各取組が進められていた。
このように、町全体で交流と協働のまちというビジョンを共有し、行政だけでなく民間や地域住民も関わりながら移住者のサポート体制を充実させることが大切であるとわかった。
■2日目:5月28日(土)
●フィールドワーク/講義②「平時を楽しみ有事に備えるEGAO VISION」
講師:林 映寿 氏 (浄光寺副住職/一般財団法人日本笑顔プロジェクト 代表) 会場:体験型ライフアミューズメントパークnuovo
2日目は、体験型ライフアミューズメントパーク「nuovo(ノーボ)」にて、林氏よるフィールドワークと講演が行われた。
林氏は、令和元年10月の台風19号による被災時に、復旧作業の効率的な実施には重機がとても重要だと認識し、これを契機として、被災時に一般市民が重機を動かせるよう運転資格を取得できる体験型ライフアミューズメントパークnuovo(ノーボ)を、小布施町内に設立した。
nuovoでは、「平時を楽しみ、有事に備える」をテーマとし、アミューズメント要素を取り入れる講習内容とすることで、より広い層にもアプローチし体験してもらえるよう工夫がされていた。実際に、重機講習の受講者のうち3割が女性であるなど、多くの方が参加しており、今後さらに資格者を増やしていきたいとのことだった。
また、参加に際しては、サブスクリプション型での講習費負担により、重機技能講習から指導者資格取得まで、継続的にステップアップできるよう考えられており、受講者と運営組織のいずれにおいても、継続できるよう配慮されていた。
フィールドワークでは、人力とショベルカーによる土砂の掘削量の比較、救助用バギーの乗車体験など、災害時における重機の重要性を、楽しみながらも肌で感じることができるよい機会となった。
●パネルディスカッション②「『協働と交流』で取り組む『環境先進都市』への挑戦」
パネリスト
林 志洋 氏 小布施町総合政策推進専門官
税所 篤快 氏 小布施町ゼロカーボン推進員
古木 里菜 氏 小布施町ゼロウェイスト推進員
宮田 湧太 氏 小布施町総合政策推進室/グリーンディスティネーションチーム リーダー
会場:小布施町役場 講堂
パネルディスカッションでは、上記の4名から「環境」をテーマの中心としながら、小布施町との関わりや現在の取組などについて話があった。
古木氏は、ごみの削減を目的としたゼロウェイストの取組を推進し、可燃ごみの組成調査、町内でのヒアリング等を実施していた。調査結果から、町のごみ問題の特性(栗の剪定枝が多いこと等)や町民の環境意識について把握し、今後のごみ削減につなげていく見通しについても触れられた。
「町内の環境への意識について」の質問が会場の参加者から寄せられ、これに対し、環境保護を大切にするという選択が経済的にも合理的な選択肢になりつつあるのではないか、という意見も出るなど、活発なディスカッションの場となった。
そのほか、各パネリストからも現在の取組について紹介があった。
取組内容だけでなく取り組む意義を発信することで、共感した町内外から協力者を巻き込むことができているとの説明があり、今後も、町内外の方の理解を得ながら、より多くの取組を進め、町内外の方にとって魅力のあるまちづくりにつなげたい、との話があった。
●グループワーク・振り返り
会場:小布施町役場 講堂
2日間の講義やまち歩き、フィールドワーク等を通じて、学んだこと、感じたことなどをグループで意見交換した。付箋を使い自分の考え方を見える化し、グループ内で共通項を探った。
最後に、今回の学びをどのように実践していくかについて考え、共有した。
今回の地方創生実践塾in 長野県小布施町では、「これまで」の町並修景事業やオープンガーデン事業などから、「これから」のnuovoでの自助・公助による災害支援、環境保護等の各取組まで、同町のまちづくりについて幅広く知ることができた。また、なぜ小布施町に多くの人材が集まりチャレンジできる環境になっているのか、という点も含め、とても多くを学ぶことができた。
スケジュール
5月27日(金)13:00~18:30
◆開講式
◆オリエンテーション
主任講師: 林 志洋 氏(小布施町 総合政策推進専門官)
◆講義
特別講師: 桜井 昌季 氏(小布施町長)
◆フィールドワーク
まちあるき(中心部の修景事業など)、まちとしょテラソ、ハウスホクサイ
◆パネルディスカッション ~地域内外の人々が溶け合う小布施流まちづくり~
主任講師: 林 志洋 氏
特別講師: 塩澤 耕平 氏((一社)ハウスホクサイ 代表理事)
日髙 健 氏
(一社)小布施まちイノベーションHUB 理事/小布施町 地域おこし協力隊)
遠山 宏樹 氏
(一社)小布施まちイノベーションHUB /小布施町 地域おこし協力隊)
◆交流会(会費制)
5月28日(土)8:45~15:00
◆講義
特別講師:林 映寿 氏(浄光寺 副住職/(一財)日本笑顔プロジェクト 代表)
◆フィールドワーク
体験型ライフアミューズメントパーク「nuovo(ノーボ)」
◆パネルディスカッション ~「協働と交流」で取り組む「環境先進都市」への挑戦~
主任講師: 林 志洋 氏
特別講師: 税所 篤快 氏 (小布施町ゼロカーボン推進員)
古木 里菜 氏(小布施町ゼロウェイスト推進員)
宮田 湧太 氏(小布施町総合政策推進室グリーン・デスティネーションチーム チームリーダー)
◆昼食
◆グループワーク
◆閉講式
講師紹介
主任講師 林 志洋 氏(小布施町 総合政策推進専門官)
特別講師 桜井 昌季 氏(小布施町長)
特別講師 新荘 直明 氏(小布施町SDGs観光コーディネーター)

小布施町総合政策推進室 SDGs観光コーディネーター
1994年茨城県鹿嶋市生まれ。大学在学中から気候変動関連の政策提言に携わり、環境大臣との意見交換等に参加。
2019年に東京大学大学院理学系研究科修士課程を修了し、新卒で岡山県西粟倉村にIターン移住。「さとのば大学」の地域コーディネーターとして地域でのプログラム開発を行い、2020年4月に一般社団法人Nestを設立(2021年に代表を退任)。
2021年に長野県小布施町に移住し、SDGs観光コーディネーターに就任。官民協働での環境政策づくりを通じた持続可能なまちづくりをめざしている。
特別講師 日髙 健 氏((一社)小布施まちイノベーションHUB 事務局長/小布施町 地域おこし協力隊)
特別講師 林 映寿 氏(浄光寺副住職/(一財)日本笑顔プロジェクト 代表)
特別講師 塩澤 耕平 氏((一社)ハウスホクサイ 代表)
特別講師 遠山 宏樹 氏 ((一社)小布施まちイノベーションHUB/小布施町 地域おこし協力隊)

長野県出身。大学卒業後、青年海外協力隊(現JICA海外協力隊)として2年3カ月アフリカ・ガーナの地方教育委員会で必修科目であるICTの授業や教員研修を行う。帰国後、2020年4月より長野県小布施町に移住。地域おこし協力隊と小布施まちイノベーションHUBに所属をし、小・中学校の現場での支援や授業、小・中の橋渡しやオンラインの学校との連携、中・高生の居場所づくりなど教育を軸に活動中。
特別講師 古木 里菜 氏(小布施町ゼロ・ウェイスト推進員/地域おこし協力隊)

茨城県石岡市出身。東京でのコロナ禍生活によりごみ削減に目覚める。独学で自宅のごみ削減(ゼロ•ウェイスト)に取り組み、個人でできる範囲が限られていることに気付く。その後勤めていた会社を退社し、小布施での活動を決意。現在は、町の政策と町民の方々とをつなぐコミュニケーションに携わる傍ら、純粋に移住ライフを楽しんでいる。
特別講師 税所 篤快 氏(小布施町ゼロ・カーボン推進員/地域おこし協力隊)

1989年東京都足立区出身。早稲田大学教育学部卒。英ロンドン大学教育研究所(IOE)準修士。19歳でバングラデシュへ。同国初の映像教育であるe-Educationを創業し、最貧村から国内最高峰ダッカ大学に10年連続で合格者を輩出。同モデルは米国・世界銀行のイノベーション・コンペティションで最優秀賞を受賞し、「五大陸のドラゴン桜」と銘打って14ヵ国で活動。未承認国家ソマリランドでは暗殺予告を受けながらも、教育と起業家を育成する「日本ソマリランド大学院」を米倉誠一郎氏と創設。2021年夏からは長野県小布施町に移住、新たな事業に取り組んでいる。著書に『前へ!前へ!前へ!』(木楽舎)、『未来の学校のつくりかた』(教育開発研究所)等。2011年度シチズン・オブ・ザ・イヤー受賞。2016年にはアメリカの経済誌「Forbes」のアジアを牽引する若手リーダー「Forbes30 under30 Asia」に選出。
特別講師 宮田 湧太 氏(小布施町SDGs観光コーディネーター/合同会社HiDenBox代表社員)

神奈川県横浜市出身。新卒でコンサルティング会社に入社し、食や住宅などの生活産業領域を中心に成長戦略や新規事業開発等のプロジェクトをリード。
現在は起業・独立して調味料ECサービスの開発を行う。小布施町には2021年4月に移住し、町の「持続可能な観光」に関するプロジェクトチーム(グリーン・デスティネーションチーム)を担当。