【終了レポート】令和3年度地方創生実践塾㏌港区
地方創生実践塾 終了レポート
2022年04月14日
関わる・つながる・連携する港区〜協創による新たな価値創造手法を考える〜
令和3年12月10日(金)~12月11日(土)の2日間、港区で、「関わる・つながる・連携する港区〜協創による新たな価値創造手法を考える〜」をテーマとして、地方創生実践塾を開催しました。全国各地の自治体職員など14名のご参加をいただきました。
港区の概況
面積20.37㎢、人口約25万人。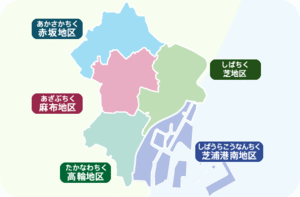 昼間人口:約94万人
昼間人口:約94万人
飲食店営業数:都内最多約15万店
ホテル・旅館客室:都内最多約3万室
主要民間放送テレビ局本社:5局所在
区政運営の形:5つの地区ごとに総合支所による区政運営体制
【令和3年12月10日(金)】
◆講義「港区ならではの全国連携及び企業連携の推進手法について」
講師:港区全国連携推進担当課長兼務区役所改革担当課長 宮本 裕介 氏
主任講師の宮本氏からは港区の連携の具体例として、岐阜県郡上市と和歌山市の2事例を紹介いただきました。
両事例とも江戸時代から交流を行っており、中学生の企業訪問、自然体験等の交流を続けるなど、互いに深い関係を築いてきた。そのお陰もあり、日頃から自治体同士で連絡がとれる関係が築かれていたことで、災害時に互いに必要な支援を速やかに行うことができたとのことでした。
また、港区では「民間協創制度」という民間企業などからの事業提案を受け付けることで、民間企業の持つ知識やノウハウ、先端技術等の強みを、区の課題解決や企業等にとっての新たな価値向上につなげることを目指しており、代表的な取組としては、区内に立地している企業である株式会社日テレ7と新橋SLビールを開発。JR東日本系のコンビニエンスストアNewDaysでの販売も実現し、販売本数はわずか1年弱(令和3年7月末)で10万本を超えるヒット商品となるなど、区内外の多くの人が区の取組を知るきっかけとなった。
港区が全国と連携し一層推進してきた背景として、港区は全国に支えられて発展してきており、つながりを大切にしながら取り組んできた地盤があることを学びました。
◆講義「遠隔自治体連携の可能性と展望」
講師:東京都立大学法学部 教授 大杉 覚 氏
大杉氏から遠隔自治体間連携の可能性や期待される効果等についてお話いただきました。
遠隔連携は親睦、交流的なものがより深い形に深化していく傾向があり、必ずしも一対一ではなく、関係性が複雑化しており、「親睦・交流」から「政策連携」へ深化するにあたって、失敗を恐れず果敢に挑戦するとともに、最初から大規模なものとせずスモール・スタートしていくことが重要となるとお話いただきました。
遠隔自治体間連携の意義は、地理学者 宮口侗廸氏の著書に書かれる「野性と普遍性のドッキング(都市と農山村の交流により自らの価値に気づくとともに、それを普遍的な価値に高めること)」を具体化していくことにあり、単独の自治体では成しえないことも自治体だけでなく民間企業等も含めた一対多数で連携し、多様な可能性を広げていくことで、新たな可能性を創造することが可能となるということを学びました。
◆座談会(民間企業と自治体の連携に関する意見交換)
株式会社日テレ7担当者
港区と連携し「新橋SLビール」や「MINATOマーケット」を展開する企業側の視点から、連携において判断基準としている視点や取組時の企業側の悩みなどを参加者からの質問も受けながらお話しいただきました。
◆フィールドワーク「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度を活用した民間施設の見学」
平成23年に港区が制定した「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」により、協定を締結した石巻市と古殿町の木材を使用して建設された高輪ゲートウェイ駅の内部を案内いただくとともに、認証制度、駅周辺のまちづくり構想について説明いただきました。
【令和3年12月11日(土)】
◆グループワーク
特別講師:一般財団法人地域活性化センター フェロー・人材育成プロデューサー
地域活性化伝道師、地域力創造アドバイザー 前神 有里 氏
前神氏にファシリテーターとして、講義で紹介いただいた具体的な事例などを参考にグループワークを行いました。
自身の所属する自治体、機関と港区との連携案について話し合い、サポート役に宮本氏や大杉氏、区職員の方も入ました。発表では下記のようなものあり、中には早速連携に繋がったものもありました。
グループワークで発表された内容
・港区と大使館とJICAで連携して、国際的な連携を推進するとともに、地方と諸外国の文化交流を実施!!
・港区で温泉文化まつりをやりたい!全国の地域性を出したサウナをやろう
・港区内の小学校の給食で山形の米を提供、農家さんの話も聞いて食育を推進しよう!
など
◆まとめ
・全国の自治体と連携している港区と派遣元で連携することで、より首都圏へのアプローチの幅が広がり、港区と連携している自治体どうしのつながりも広がる可能性があることを知りました。
・単独の行政で対応できることは限られることが認識されてきていて、自治体間や自治体と企業間での連携が増えてきているが、形式的な連携ではなく、政策を意識して共通の未来を描くことが重要であると学びました。
・港区が全国自治体との連携に意欲的であることが、地方の自治体にとっては何よりも大きなチャンスであると感じました。
カリキュラム
◆12月10日(金)
13:00 ~17:15
1.開講式
2.講義【港区ならではの全国連携及び企業連携の推進手法について】
主任講師 宮本 裕介氏
3.講義【遠隔自治体連携の可能性と展望】
特別講師 大杉 覚氏
4. 座談会
日テレ7ご担当者
5.FW:JR高輪ゲートウェイ駅舎 他
◆10月23日(土)
12月11日(土)
9:00 ~11:30
1.グループワーク
特別講師 前神 有里 氏
2.発表・総評
3.閉講式
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。






