- ホーム
- イベントカレンダー
- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー
- 【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「急速に広まった自治体の生成AI活用」
【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「急速に広まった自治体の生成AI活用」
新たな知と方法を生む地方創生セミナー
2024年09月12日
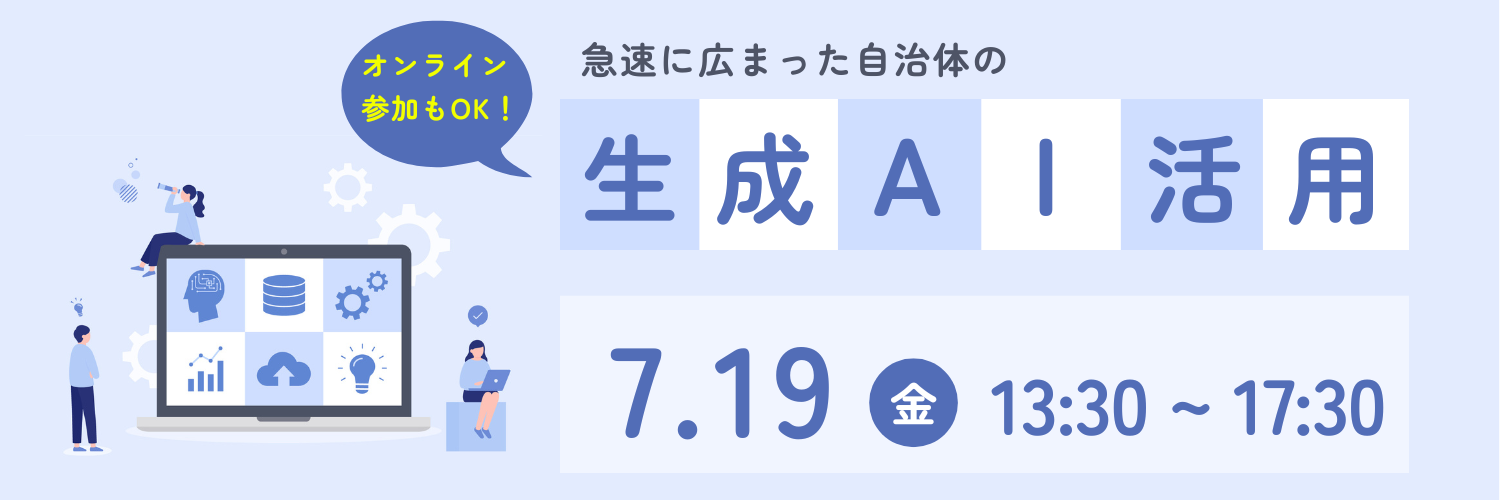
はじめに
令和6年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「急速に広まった自治体の生成AI活用」を、2024年7月19日(金)に開催しました。地方公共団体などから現地会場4名、オンライン53名の参加がありました。
今回のテーマ
本セミナーは、急速に広まった生成AIについて、どのような公務に活用し、職員の負担をどれだけ軽減することができるのか、実際に体験もしながら学ぶとともに、導入に至るまでに必要な調整や手続き、活用方法を学ぶことを目的として開催しました。
講義
【主任講師】東武トップツアーズ株式会社CDO 村井 宗明 氏
30歳から衆議院議員を3期、衆議院災害対策特別委員長、文部科学大臣政務官を務めた行政デジタルの専門家。政界引退後、ヤフー株式会社、LINE株式会社などで行政専門のITエンジニアとして、国、地方公共団体、教育機関などの多くのシステムを開発。また、230以上の自治体が月3万回利用している公務員専用ChatGPT「マサルくん」を開発。
【講義① 生成AIの概要】
村井氏は、はじめに「生成AIの概要」をテーマに講演されました。AIの急速な進化とそれがもたらす影響について、世界における生成AIの需要の見通しは、2030年までに年平均で約53%成長すると予測されています。その影響は民間だけでなく、地方公共団体にも及ぶとされ、特に、AI技術を使いこなすスキルが求められる現代において、従来の教育体系や雇用のあり方が急速に変化していると述べられました。
また、AIの普及に伴い、転職が当たり前になりつつある現代の労働市場についても触れました。終身雇用が当たり前だった時代から、今では転職を繰り返すことでキャリアを築くのが一般的となっており、AIを使いこなせる人材がより高い評価を受ける時代が来ていると指摘しています。一方で、AI技術が普及すると、一般事務や秘書業務などがAIに代替される可能性が高くなり雇用の不安定化が生じると述べられました。
講義の後半では、AIを使ったコンテンツ生成の実演が行われました。文章生成や画像生成、音楽作成、パワーポイントの自動作成など、AIがどのようにして様々なコンテンツを効率的に作り出すかが紹介され、AIの可能性とその実用性を体験しました。
【講義② 公務員内部専用AIについて】
続けて村井氏は、「公務員専用AIマサルくん」の使い方をテーマに講演されました。
マサルくんは、公務員専用AIとして村井氏が開発し、特に地方公共団体内での業務効率化に焦点を当てたツールです。マサルくんは、メール文案、議会の答弁書、各種書類などの作成支援やデータの自動処理を行い、職員の事務負担を軽減してくれます。例えば、デジタル田園都市国家構想交付金の申請においては、過去に採択された事業のデータを基に、その団体に合わせた事業の申請書を作成してくれます。実際に参加者は自分の団体の情報をマサルくんに入力し、申請書の作成を行いました。今後、AI技術がさらに進化し、業務の多くが自動化されることで、住民サービスの質が向上することが期待されています。これに伴い、公務員の役割もAIを活用した新しい業務スタイルへと変わりつつあり、AIが作業の自動化を担う一方で、AIにはできない創造的な業務を行うことが大事であると強調されました。
【講義③ 対住民用に提供するAIについて】
この講義では、住民向けAIチャットボットの導入と運用に当たって、経験したこととその課題についてお話がありました。はじめ、住民からの問合せに365日24時間対応できるAIチャットボットを導入し、災害時や日常業務での職員の電話対応の負担を軽減することを目指しました。しかし、一般的な生成AIの回答では情報の正確性に欠けることが多く、住民向けに提供する情報には誤りが許されないため、導入に苦労したとのことです。さらに、住民はチャットボットへの問合せの際には、長文ではなく単語で入力する傾向が強く、これにより住民が意図する回答を出すのが難しいという問題が発生しました。そこで、ホームページ全体を学習させるアプローチではなく、特定の質問とその回答を事前に設定する「QAブロック方式」に切り替えました。その結果、住民向けAIの運用では、「わからない」という回答を許容し、複数の選択肢を提示する方式にすることで、より効果的な対応が可能になったと述べられました。
事例紹介
【特別講師】神奈川県横須賀市 経営企画部デジタル・ガバメント推進室 室長 太田 耕平 氏
企業での勤務ののち市役所に転職。都市部、市民部、財政部を経て、2019年に市役所内のシンクタンク組織である都市政策研究所に異動。横須賀市基本構想・基本計画(YOKOSUKAビジョン2023)策定を担当。2023年よりデジタル・ガバメント推進室に異動し、スマートシティ、生成AIチームのリーダーを務め、2024年から現職。
【事例紹介①】
本事例紹介では、横須賀市が取り組んでいるAIツール、特にChatGPTの導入とその効果について紹介がありました。横須賀市は、少子高齢化と人口減少という日本全体が直面する課題に対処するため、テクノロジーの活用を進めています。その一環として、2022年に「YOKOSUKAビジョン2030」を策定し、テクノロジーを活用したまちづくりを推進する方針を打ち出し、2023年4月20日にChatGPTの全庁利用を開始しました。
ChatGPTの導入当初から、横須賀市のさまざまな業務でその活用が進められており、具体的には、市長の挨拶文の作成やプレスリリースの作成が挙げられます。ChatGPTを使ってプレスリリースを作成し、それをメディアに発表した結果、NHKや民放9局で報道され、市民からは応援メッセージが届くなど、市民のシビックプライド(市民としての誇り)を高める効果があったようです。
また、横須賀市では、全職員がChatGPTを使用できます。その利用方法を職員に広く共有するため、「チャットGPT通信」という定期的な情報発信を行い、ChatGPTの使い方や最新情報を紹介しています。さらに、ChatGPTの新たな活用事例の横展開や利用のモチベーション向上を目的とした「ChatGPT活用コンテスト」を実施し、職員のAI活用スキルの向上を図っています。
最後に、AIツールの導入と運用においては、職員のモチベーションを高めることが重要であると強調され、システムの導入は始まりに過ぎず、運用を続ける中で課題を解決し、改善を進めることが重要と述べられました。
【事例紹介②】
横須賀市では、令和6年度から市民向けサービスに生成AIを活用する取組を開始しました。具体的には、AIを使った市長のアバターによる英語での情報発信や、メタバース内でのAIアバターによる観光案内等が行われています。これにより、言語の壁を越えて外国籍の住民に情報を届けたり、24時間365日対応できる行政サービスを目指したりしています。
また、住民向けのチャットボット「おなやみ相談ボット ニャンぺい」を開発しました。住民への提供にあたり、市役所内での検証を行い、ホワイトハッカーコンテストという、ニャンぺいにあえて変なことを言わせるという取組を行うことで問題点を検証しました。初期の段階では誤った情報を提供してしまうなどの課題がありましたが、これに対処するため、ニャンぺいを未完成品として公開し、様々なフィードバックを収集しながら改良を進め、その結果、誤情報の発生率を大幅に減少させることができたそうです。
実技
本実技では、講義②で紹介された「マサルくん」を活用し、参加者の所属団体の政策立案を手助けしてもらう実践を行いました。初めに、政策立案を行うため、自分が考える所属団体の課題を入力し、その課題に対する現状を把握するために必要な情報を、RESAS(地域経済分析システム)から取得し、マサルくんに反映させました。実際に、マサルくんが立案した政策は、所属団体の現状が詳しく記載され、考察を踏まえながら具体的な政策立案がなされていました。
トークセッション
トークセッションでは、参加者が事前に回答したアンケート結果を基に議論が進められました。まず、アンケート結果では、64%の参加者が職場でAIを活用しており、主な用途は情報収集、アイデア出し、翻訳、文章作成などでした。一方で、活用していない、できない理由としては、セキュリティの懸念、AIの信頼性への不安、具体的な活用方法が分からないという意見が多く見られました。
議論では、村井氏と太田氏がそれぞれ異なるアプローチでAIを活用、改善している点が話題になりました。太田氏が所属する横須賀市では、AIを職員が楽しく使うことを重視しており、失敗を恐れずに取り組む姿勢を持っています。これに対し、村井氏は、住民向けAIチャットボットの運用では正確な情報を提供するために慎重なアプローチを取り、具体的なQA(質問と回答)ブロックを設定して対応しています。
また、プロンプト(AIに指示を与えるための入力)の使い方についても議論されました。プロンプト入力のコツとしては、最初はシンプルに話しかけるように指示を出し、その後AIからのフィードバックを元に回答の質を高めていく方法が紹介されました。
セミナーを終えて
本セミナーでは、生成AIを公務で活用するための具体的な方法を学ぶことができました。今後さらに身近になっていく生成AIは、業務の効率化だけではなく、住民サービスの向上にも寄与することが分かりました。AIの活用には多様な可能性があり、技術的な側面だけでなく、組織文化や人々の意識をどう変えていくかが成功の鍵であることが、セミナー全体を通して分かりました。今後、地方公共団体におけるAIの導入や運用においても、柔軟な発想と多角的な視点が求められると感じます。
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。





