- ホーム
- イベントカレンダー
- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー
- 【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ゲーム×地方創生 ~地方創生の新しいカタチ~」
【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ゲーム×地方創生 ~地方創生の新しいカタチ~」
新たな知と方法を生む地方創生セミナー 終了レポート
2025年03月13日
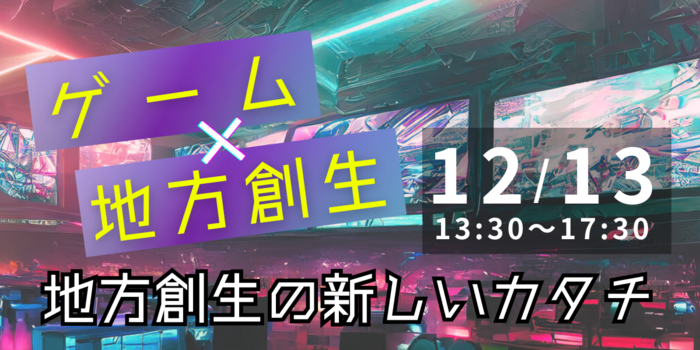
はじめに
令和6年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「ゲーム×地方創生 ~地方創生の新しいカタチ~」を、2024年12月13日(金)に開催しました。地方公共団体などから現地会場4名、オンライン15名の参加がありました。
今回のテーマ
日本の社会において、急激な少子高齢化の進行は喫緊の課題であり、特に地方では若者の都市部への流出による高齢化が加速しています。そのなかで、若者にとって魅力のあるとされているゲームを活用した地方創生の可能性を探ることを目的に、講義及び事例紹介を行いました。
講義
【主任講師】 総務省 地域力創造アドバイザー / NPO法人 IGDA日本 理事 / SIG-地方創生 正世話人
TBSテレビ 特任執行役員 ゲーム事業責任者 蛭田 健司 氏
セガにて『サクラ大戦』シリーズ、コーエーテクモにて『無双』シリーズの開発に携わり、『真・三國無双Online』の技術責任者を経てカナダスタジオに出向。現地責任者として経営を担った。その後、ヤフーにてゲーム部門長、事業戦略室エグゼクティブプロデューサー、グループ会社の執行役員CTO、人材開発室長などを経験。その後、上場企業の顧問、ゲーム関連新分野産業育成事業の総合戦略アドバイザー等を歴任し、総務省 地域力創造アドバイザーやTBSグループのゲーム事業責任者に就任。幅広い地域の地方創生に関わっている。
【講義① ゲームによる地域活性化と展望(蛭田氏)】
蛭田氏は、ゲーム業界の概要を踏まえたうえで、全国の地方公共団体におけるゲームやeスポーツの活用事例を紹介し、ゲームによる地域活性化の可能性について講義されました。
地方で若年層の人口流出が加速している状況において、ITエンジニアやゲームクリエイターといったゲーム関係の職業は若年層の人気が高く、ゲーム業界の市場規模は長期的に拡大を続けており、ゲームは地域振興のカギになると述べられました。
地方でゲーム産業の育成に取り組む場合、人材育成、人材の活躍、事業創発の3段階で行うことが必要だと指摘しています。セミナーの開催等で人材を育成しながら、地元の人々への周知や地元案件の受託等を通して地元で活躍できる土壌を整え、その後事業を誘致することで、持続的な産業の育成につながるとのことです。今後の展望として、スウェーデンの人口5万人程度の街で複数の大ヒットゲームが誕生したゲーム産業振興事業「Sweden Game Arena」の事例を紹介し、参加者同士が情報を共有しあい、助け合える文化を醸成することが鍵であると述べられました。
続けて、eスポーツの概要と課題、展望についても触れられました。eスポーツのプロ組織が求められる役割として、競技力の向上とともに、eスポーツの普及活動にも積極的に取り組むべきだと指摘しています。さらに、プロ競技の発展にはスポンサーとの関係構築が不可欠であり、選手は信頼され、応援される存在にならなければならないとも指摘しました。
また、eスポーツのイベント開催においては、まずは小さいところから実施し、継続して着実に成長させていくことが重要であり、地方公共団体がイベントを開催する場合においては、集客や実施報告を効果的に行うために必要な広報力が不足していることが多いと指摘します。プレスリリースを出す際、ニュース性を意識することでメディアが取り上げやすくなり、広く関心を集めることができると述べられました。発展の理想形として、ポーランドの地方都市で、eスポーツの国際トーナメントを開催し、国内外から多くの観客を集めることに成功した事例を取り上げ、事業に関わる人々の熱意が重要であると述べられました。
最後に、地方公共団体が活用できる制度として、ローカル10,000プロジェクト及びふるさと起業家支援プロジェクト、総務省地域力創造アドバイザー制度を紹介し、ゲームによる地域活性化のためには、成功事例を積み重ねることで人々の意識を変えていくことが大切であるというまとめで締めくくりました。
事例紹介
【特別講師①】群馬県 eスポーツ・クリエイティブ推進課 eスポーツ係長 木村 雅行 氏
群馬県は、全国の自治体で唯一「eスポーツ」と名のつく専門部署「eスポーツ・クリエイティブ推進課(当初はeスポーツ・新コンテンツ創出課)」を2020年に設置し、eスポーツの特性を活用した「地域創生(ひとづくり、まちづくり、しごとづくり)」と「群馬のブランド力向上」に取り組んでいる。
【事例紹介①(木村氏)】
群馬県では、eスポーツ推進の方向性として、地域コミュニティの活動支援による地方創生、大会・イベントの誘致によるブランド力向上、そしてゲーム依存対策の3つを重要視しているとのことです。令和6年度は、国内唯一のeスポーツ実況者の大会「全日本eスポーツ実況王決定戦」や、学校の枠を超えた19歳以下が集まる「U19eスポーツ選手権2024」など、eスポーツに関する様々な大会・イベントを実施しています。
また、地方公共団体や地域コミュニティとの連携による取り組みも進められています。「ぐんまeスポーツフェスタ」では、eスポーツとリアルスポーツの融合を図るなど、幅広い世代をターゲットにしたイベントが成功を収めました。教育現場では、県内高校のeスポーツ部が主催する「太工SuperDrive」など、高校生による自主的な活動も活発に行われているほか、福祉分野でも、シニアや障がい者向けのeスポーツ体験会を行っており、社会参加の促進に寄与しています。
群馬県では、県内企業、市町村、県民との連携・協力を進めており、県がこれまでに蓄積したノウハウを活用しながら、県内各地で様々なeスポーツイベントを自主的に開催してもらうことを目指しています。さらに、県外企業やIPホルダー、イベント会社、他都道府県民との関係においては、大規模な大会を群馬県で定着させ、群馬県をeスポーツの聖地として認知してもらうことが目標だと述べられました。
【特別講師②】群馬県庁eスポーツ部 小林 実 氏
群馬県庁eスポーツ部は、職員の有志で立ち上がった任意団体で、業務外にeスポーツによる取り組みを実施している。県庁内でeスポーツ普及のための活動をしているほか、実際に対外的な大会にも参加するなど、他自治体や民間企業とも交流を深めている。
【事例紹介②(小林氏)】
群馬県庁eスポーツ部は、2020年4月に設立されたeスポーツ・新コンテンツ創出課(現・eスポーツ・クリエイティブ推進課)における社会人eスポーツの普及促進に向けた取り組みの一環として、県庁内及び企業等との交流促進を目的に設立しました。
活動内容としては、毎月オフライン及びオンラインで行う定例活動、各団体が主催するeスポーツ大会・イベントへの参加、そして職員向け大会の開催及び外部のeスポーツイベントの運営サポートも行っているとのことです。
メンバー数は毎年増加しており、令和6年現在では72人在籍しています。なお、メンバーの7割以上がeスポーツ課以外の職員です。メンバーからは、活動を通じて業務上では知り合うことのない他部署の職員との交流ができたという声や、大会への参加を通じて、民間企業との交流の機会も生まれたという声が上がっており、eスポーツが人との交流や、新たな趣味の創出につながっていることが分かります。
これまではeスポーツ・クリエイティブ推進課の職員が運営を担っていましたが、2025年を目標にeスポーツ部員による自立した運営体制を築き、新たな体制で大会出場や、県外の団体との交流の活発化を目指していきたいと展望を述べられました。
トークセッション
トークセッションでは、スタートの経緯、必要なもの、目標、ゴールの4つのテーマで対話 が行われました。はじめに、スタートの経緯については、群馬県はeスポーツを活用するという枠組みが先に決まった点が意義深く、他の地方公共団体もまずは「eスポーツをやる!」と決めたうえでできることから始めるのが重要であるという意見がありました。次に必要なものというテーマでは、群馬県はゲーミングPC等の機材調達に企業版ふるさと納税を活用したこと、そしてハード面以外にもゲームメーカーとの関係構築の必要性について論じられました。次に目標について、県内経済への波及効果を計測するのは難しいが、参加者数や会場の盛り上がり、関連ページのPV数は指標になるという議論になりました。最後にゴールについては、各地域コミュニティが自発的にeスポーツを活用・継続していくこと、eスポーツが将棋やプロ野球のように多くの人の注目を集め、消費が生まれるスポーツになることが上がりました。
セミナーを終えて
本セミナーでは、ゲームを活用した地方創生の可能性について学ぶことができました。ゲーム業界もeスポーツ業界も成長を続けており、観光振興や地域経済の活性化、ブランディング、行政の理解促進、防災等、地方公共団体の幅広い分野の施策においてゲームの活用が効果的であることが分かりました。まtた、セミナーを通して、できることから着実に積み上げていくこと、担当者が熱意をもって取り組むことが成功につながることが分かりました。今後、ゲームは単なる遊びではなく、地方創生に大きく貢献する重要なカギになっていくのだと感じました。
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。





