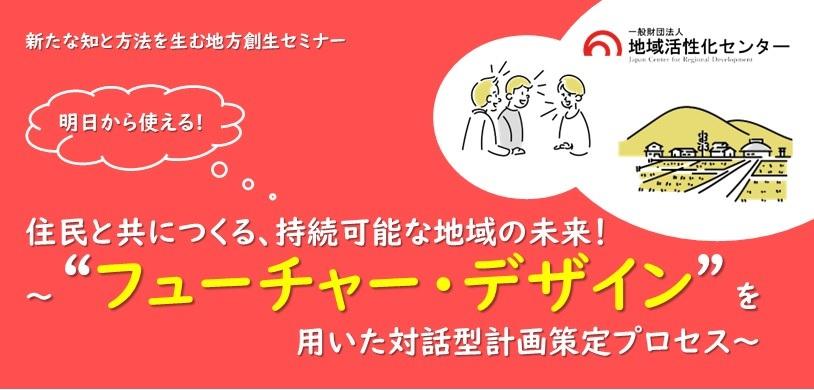【終了レポート】令和4年度【スタンダード型】新たな知と方法を生む地方創生セミナー 住民と共につくる、持続可能な地域の未来!~"フューチャー・デザイン"を用いた対話型計画策定プロセス~
募集終了 終了レポート
2022年09月07日
令和4年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「住民と共につくる、持続可能な地域の未来!~"フューチャー・デザイン"を用いた対話型計画策定プロセス~」をリアルとオンラインを併用して開催しました。
全国各地から自治体職員など10名の方々に参加いただきました。
講義Ⅰ
フューチャー・デザイン研究所 所長 西條 辰義 氏

フューチャー・デザインの提唱者。ミネソタ大学大学院経済学研究科修了。
Ph.D.(経済学)。オハイオ州立大学講師、カリフォルニア大学助教授、筑波大学教授、大阪大学教授、一橋大学教授等を経て、高知工科大学フューチャー・デザ イン研究所・所長、総合地球環境学研究所・名誉フェロー・アドバイザーを務める。
専門は制度設計工学、公共経済学。著書は『フューチャー・デザイン』『フュー チャー・デザインと哲学』(編著・勁草書房)、『地球温暖化の経済学』(共著・大阪 大学出版会)、『排出権取引』(共著・慶應義塾大学出版会)など多数。
「仮想将来人になって将来をデザインする」
西條氏からは、フューチャー・デザインとは何か、どのような利点があるのかについて講義いただきました。
フューチャー・デザインとは「仮想将来人」になり、将来世代の視点から、目指すべき社会実現のため、今何ができるのかを考えていく方法で、活用することにより、目先の便益にとらわれない将来設計ができるとともに、将来に向けた前向きな考えが自然に生まれるとお話しいただきました。
また岩手県矢巾町や京都府宇治市における取組事例についても紹介があり、実際に施策立案に活用されているとの説明がありました。
講義Ⅱ 自治体の取組事例
岩手県矢巾町企画財政課 課長補佐 高橋 雅明 氏

矢巾町は平成28年にフューチャー・デザイン の共同研究に関する連携協定を大阪大学と締結し、町政の意思決定にフューチャー・デザインを本格的に採用(全国初)。
住民ニーズを把握する手法として活用し、総合 計画や水道インフラなどいくつかの分野で住民参加型のワークショップを実施。
「フューチャー・デザインタウン矢巾町」
高橋氏からは、矢巾町が実践しているフューチャー・デザインを活用した取組として、ワークショップでの実施内容、そこから生まれた企画や総合計画について紹介いただきました。
行政がフューチャー・デザインを活用することにより、バックキャスティングによるゴール設定や社会環境、現実的な制約・問題を超越した、市民が真に求めるまちづくりが可能であることを学びました。
講義Ⅲ 市民団体の取組事例
フューチャー・デザイン宇治 世話人 瀬戸 真由美 氏

平成30年に京都府宇治市が主催した市民向けフューチャー・デザインシンポジウムの参加をきっかけに、市民有志で、「フューチャー・ デザイン宇治」の立ち上げに参加。
現在、宇治市内でフューチャーデザインを実施し「住 民が主体的に地域づくりを考えるきっかけの 場」づくりを行う。
「フューチャー・デザインと市民ワークショップ」
瀬戸氏からは、フューチャー・デザインとの出会い、立ち上げた「市民団体フューチャー・デザイン宇治」での活動について紹介いただきました。
フューチャー・デザインを活用したワークショップでは、世代や立場などを超えたフラットな議論が可能になるとともに、市民一人一人がまちの問題を自分ごととして意識するきっかけになるとお話しいただきました。
ワークショップ
ワークショップでは、まず仮想自治体A市を設定し、その後、2050年の未来人になって「その地域でどんな暮らしをしているのか」と「現代へ送るメッセージ」について話し合いました。
実際に体験してみると、考えを言語化することや現代にとらわれない未来だけを語る難しさを痛感しつつも、明るい未来を考える楽しさを実感しました。
また「今抱えている人口減少や過疎といった問題が、技術の進歩により将来では大した問題ではなくなってきているのではないか」という意見もあり、現在の取組が本当に必要なのか再認識する良い機会になったと感じました。
スケジュール
8月5日(金)
| 10:30~ |
開講式 |
|---|---|
| 10:35~ |
講義Ⅰ(FD研究所 西條氏) |
| 11:15~ |
講義Ⅱ(矢巾町 高橋氏) |
| 11:45~ |
講義Ⅲ(FD宇治 瀬戸氏) |
| 12:15~ |
休憩 |
| 13:20~ |
ワークショップ体験 |
| 16:05~ |
まとめ・閉講式 |
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。