【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「自治体職員のための行動経済学 ~ナッジの活用~」
2024年12月04日
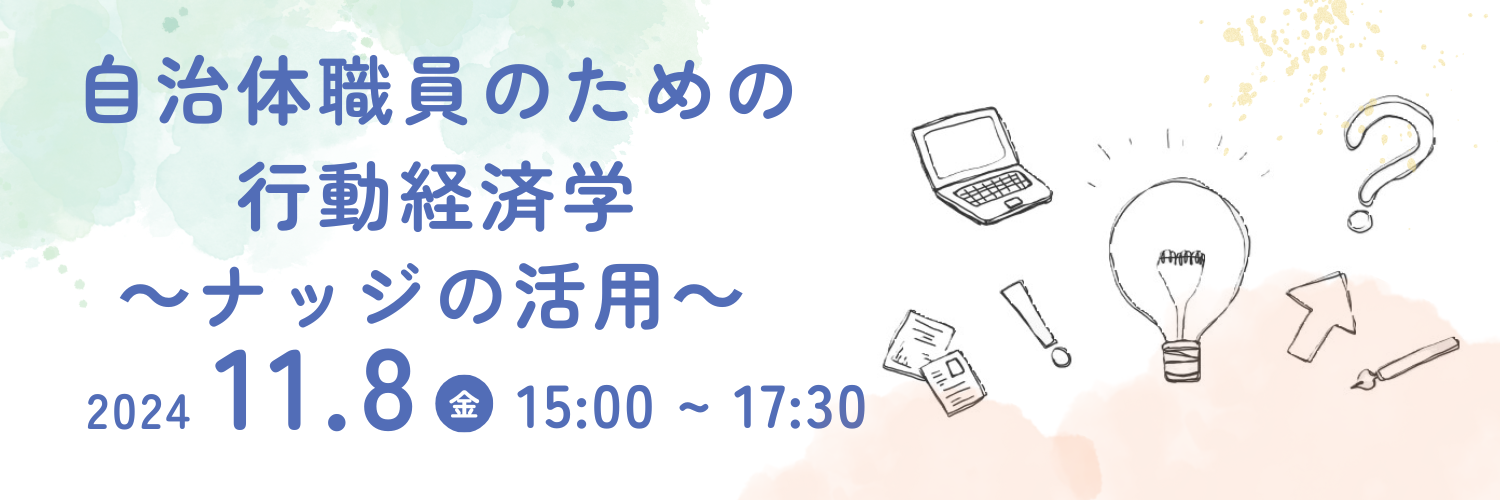
はじめに
令和6年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「自治体職員のための行動経済学~ナッジの活用~」を、2024年11月8日(金)に開催しました。地方公共団体などから現地会場7名、オンライン37名の参加がありました。
今回のテーマ
本セミナーは、経済的なインセンティブや行動の強制をせず、行動変容を促す手法として注目を集めているナッジについて、基本的な概念や自治体での活用事例を学ぶことを目的として開催しました。
講義
【主任講師】 NPO法人Policy Garage 伊豆 勇紀 氏
宮城県職員とのパラレルキャリアで、NPO法人PolicyGarageで活動中。ナッジと出会ってから実践までの苦労や、宮城県庁でナッジを推進する宮城県行動デザインチーム(MyBiT)設立の経験を活かし、全国の自治体でナッジの研修・講演や体制構築支援を行うほか、大阪大学社会経済研究所、行動経済学会と協働して、ナッジに関する知見共有のポータルサイト「自治体ナッジシェア」の構築・運用をリード。地方から行政が変革していくのが国際的な潮流になる中で、ナッジなどの革新的な政策手法に興味を持った全国の自治体職員が、共に学び、実践し、成果や知見を広く共有できるエコシステムの形成を目指しています。
【講義】
ナッジの背景として、リチャード・セイラー教授が提唱した「Nudge」理論が紹介されました。ナッジの本質は、選択肢の限定や、経済的な強制を伴わずに、他人の行動が気になる人間の同調性や様々なバイアスを考慮し、選択の仕方を工夫することで、自然に行動を改善させることにあります。
具体例としてイギリスの納税メッセージにおける事例では、「納税が遅れています。支払ってください」というメッセージに他の人の行動を加えた「あなたの街では10人中9人が期日内に納付しています」と変更した場合、納税率が67.5%から83.0%に増加するなど、同調性の活用が人々の行動に影響を与えることが紹介されました。
また、選択のデフォルト設定(初期設定)の重要性も強調され、複数の選択肢から選択する作業は認知的な負荷がとても大きく、デフォルトの工夫が人々にとっての「選ばない選択肢」を最も魅力的にすることが可能であります。
次に、省庁や民間のナッジユニットが取り組む具体的な実践手法が説明されています。「行動プロセスマップ」を作成し、行動のボトルネックとなる部分を特定することが推奨されます。これにより、何が行動を阻害する原因なのかを分析し、その障害を取り除き、行動をスムーズにすることで目標行動への移行が促進されます。そこに、「EAST」フレームワーク(Easy「簡単に」, Attractive「印象的に」, Social「社会的に」, Timely「タイムリーに」)を活用することで、ナッジの設計が容易になるとしています。「EAST」フレームワークの中でもEasyが一番大事とされており、簡単にすることが行動につなげるための一歩目と紹介しました。
具体的な事例として、横浜市での特定保健指導受診率向上を目的としたナッジ施策が紹介されました。封筒のデザインを改善することでそもそもの封筒開封率が向上し、結果的に検診率も上昇しました。ほかにも、固定資産税の口座振替勧奨において、簡素なメッセージと損失回避の強調を行い、納税手続きの促進に成功した事例を紹介いただきました。
さらに、地域や組織の場面に応じた継続的な実践と改善が重要であるとしています。各地のナッジユニットが地域ごとに異なる課題に対処し、試行錯誤を通じて行動デザインを工夫し続けている例が述べられています。ナッジは万能の解決策ではなく手段の一つであり、状況や対象に応じて適切な工夫と柔軟なアプローチが必要であるとされています。
この講演の締めくくりでは、ナッジは単なる理論ではなく、日常業務や政策立案において小さく始められる実践的な手法であり、自治体職員が主体的に取り組む意義があるとされています。
セミナーを終えて
本セミナーでは、ナッジを公務で活用するための具体的な方法を学ぶことができました。小さなことから始めることができるので、日々の業務の見直しの中で活用していきたいと思いました。また、正解があるものでもないため個々の考えを共有しながらより良い成果物を作っていく必要性を感じました。
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。





