- ホーム
- イベントカレンダー
- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー
- 【終了レポート】令和6年度【アドバンス(平日2日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「VUCA時代の今、地方公共団体職員に求められる能力とは」
【終了レポート】令和6年度【アドバンス(平日2日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「VUCA時代の今、地方公共団体職員に求められる能力とは」
新たな知と方法を生む地方創生セミナー 終了レポート
2025年02月21日
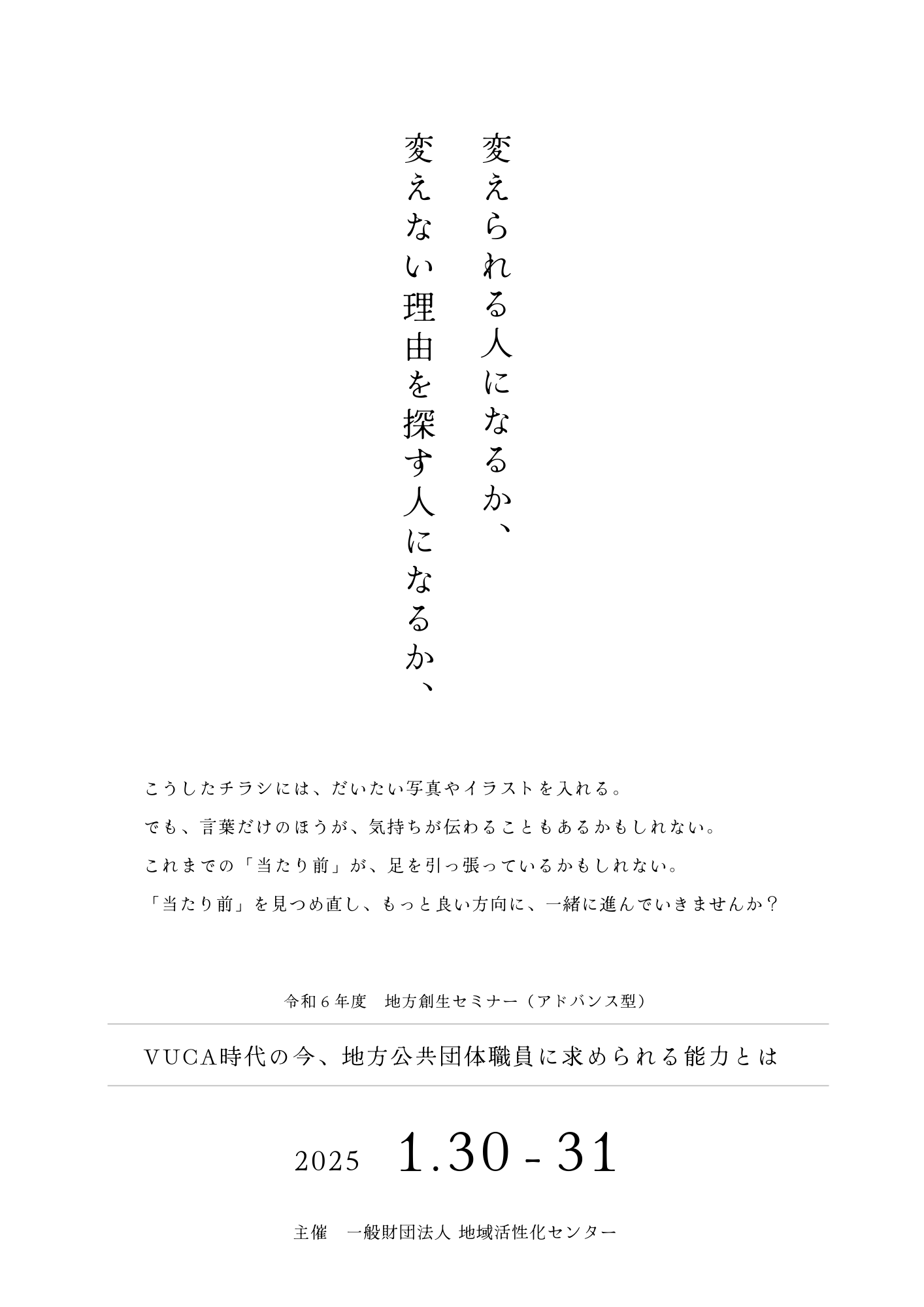
はじめに
令和6年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「VUCA時代の今、地方公共団体職員に求められる能力とは」を、2025年1月30日(木)~31日(金)に開催しました。地方公共団体などから16名が参加し、VUCA時代を生きる公務員に求められる視点と思考力について学びました。
講義
「VUCA時代の今、地方公共団体職員に求められるものとは」
主任講師:(一財)地域活性化センター シニアフェロー 箕浦 龍一 氏
近年のデジタル技術の進化により、インターネットの商業利用が拡大し、携帯電話の普及が進んだことで、ビジネスやライフスタイルに大きな変化が生じています。しかし、日本はこの変化に十分対応できておらず、昭和の制度にとらわれ続けているため、ゼロベースでの改革が求められているとの指摘から講義は始まりました。情報の民主化が進み、個人が直接情報を取得し発信することが可能になったことで、共通の課題意識を持つ人々がSNSを通じてつながることが容易になりました。その結果、従来のマスメディアの影響力が低下し、情報の正確性や信頼性を見極める力がますます重要になっています。さらに、職と住の分離や雇用の流動化が進み、変化に適応できなかった業態は衰退を余儀なくされている状況も説明されました。VUCAの時代において、国や地域、企業、地方公共団体にとって「変化」に対応できないことが最大のリスクとなるとし、「脱皮しない蛇は滅びる」という言葉を引用しながら、時代の先を読み解き、常にアップデートし、価値を生み出す力の重要性を強調されました。
地方公共団体運営においても、プロジェクト単位や人材単位での共創・イノベーションにシフトすることが不可欠であり、そのためには人材のアップデートやリスキリングへの投資が求められます。そして、日本型組織に根付いた「虚構の同質性」や「暗黙のルール」が、心理的安全性を損ない、コミュニケーション不全を引き起こす要因となっていると指摘されました。この閉鎖的な環境を打破するためには、越境体験や越境学習を通じて新しい知見を得ることが重要であり、働き方においても、人的資本経営の視点を取り入れ、合理性を重視しながら価値を生み出す仕組みを確立する必要があります。さらに、雑務を削減し、生産性を高めることで、より持続可能な働き方を実現することの重要性についても強調されました。
事例紹介
「四條畷市における組織改善の取組~四條畷市はどのようにして変化し続けているのか~」
特別講師:大阪府四條畷市 総務部人事課長 溝口 直幸 氏
四條畷市では、東(前)市長が在職中に労働時間革命を宣言し、生産性向上を目的とした施策に取り組んだことが紹介されました。職員数が減少し、行政サービスが多様化する中、単なる残業時間の削減ではなく、市民サービスの向上を軸にした改革が行われたとのことでした。具体的な取組として、管理職研修やモデル課による実践、「カエル会議 」「朝夜メール(タスク管理)」「集中タイム」などの施策が試行され、職員間の情報共有を強化することで、業務の属人化を解消し、仕事の効率性を向上させました。その結果、新規事業で業務量が増加する中でも残業時間を削減したと報告がありました。また、エンゲージメント調査を導入し、管理職会議の見直しや若手職員と市長の座談会を実施することで、職員の意見を反映しやすい環境を整えたとのことでした。さらに、人材確保の課題に対する取組として、オンライン面接や転職サイトとの連携により応募者数を大幅に増やし、また、中途採用者の定着支援として定期面談やAIを活用したフォローアップを導入し、1年以内の離職率をゼロに抑えたと説明されました。最終的に、これらの施策を「人事戦略基本方針」として整理し、エンゲージメント向上を軸に、職員の能力向上と市民サービスの向上を目指しているとのことでした。
「人手不足、業務の属人化、負担拡大、対話不足-ボトムアップとトップダウンを組み合わせ、全庁的課題の解決へ!」
特別講師:福島県会津若松市 総務部人事課 江川 大樹 氏
会津若松市では、職員採用の競争率低下や業務量の増加、業務の見直しが進まないことによる職場の閉塞感、特定職員への業務偏重などの課題が顕在化していました。これらの課題を受け、令和2年度から本格的な働き方改革に着手し、幹部職員向けの講演を実施し、改革の必要性を共有した上で「働き方改革推進本部」を設置し、全庁的な意識改革を進められました。さらに、職場ごとの業務改善を促進するため「カエル会議」を導入し、職員が意見を出しやすい環境を整えたとのことでした。モデル職場での取組として、窓口対応のアポイント制導入や業務マニュアルの作成を行い、全庁的な取組としては、管理職を対象としたマネジメント研修の実施や人事評価制度の活用、休暇取得促進などを進めたと紹介されました。特に、男性職員の育児休業取得率は令和元年度の7.1%から令和5年度には66.7%に向上し、全国平均を大きく上回る成果を上げられています。一方で、人事異動による取組の停滞などが課題として残っているとの指摘もありました。これらの課題を踏まえ、令和6年度から幹部職員を中心とした「働き方改革課題解決特別タスクフォース」を設置し、部局を越えた協力体制を構築したとのことでした。今後は、業務の削減や働き方改革の全庁的な浸透を図り、持続可能な組織づくりを進めるとともに、職員の働きがい向上や市民サービスの質の向上につなげていきたいと述べられました。
円座セッション
講師と参加者が円形に座り、地方公共団体の働き方改革や組織の変革について議論しました。特に、男性職員の育児休暇取得率の向上に伴う業務負担の問題や、職場の雰囲気の変化について意見が交わされました。育休取得が昇給や昇格に影響しない制度が取得率向上に寄与していることや、「お互い様」という意識が根付きつつあることが共有されました。加えて、男性の育休取得は事前に計画できるため、むしろ管理しやすいとの見解も示されました。 また、組織の変革には、トップダウンとボトムアップの両方が必要であるとの意見が多く、強いリーダーシップと職員の意識改革の両立が重要だと指摘されました。特に、成功体験を積み重ねることで改革が定着しやすくなることが強調されました。さらに、管理職のなり手不足が課題として挙げられ、その背景には業務負担の大きさや組合の影響があることが議論されました。解決策として、研修の充実やロールモデルの確立が求められています。最後に、変革を持続させるためには、会議を通じた継続的なコミュニケーションが重要であり、チームでの取組を推進することが改革の定着につながると確認されました。
個人ワーク・グループワーク
1日目の講義を受け、自分自身や所属する組織における「当たり前」をどのように変えていくべきかを考えながら、カエルプランを作成しました。作成後は、1人ずつカエルプランを発表し全体で共有することで、異なる視点や新たな気づきを得る機会となりました。さらに、各自が作成したカエルプランを持ち寄り、理想の組織像を描きながら、現状や課題を分析し、それに対する実行案などについて議論を深めました。意見交換を通じて、多様な視点からのアプローチを学ぶことができ、より実効性の高いアイデアが生まれました。このワークは、研修後にも地方公共団体などで話し合いの手法として活用できるような実践的な内容であり、現場での課題解決や組織改革に役立つものとなりました。
セミナーを終えて
セミナーでは、VUCA時代における地方公共団体職員に求められる能力や、組織改革の重要性について学びました。また、四條畷市や会津若松市の事例を参考に、地方公共団体における働き方改革や人材育成の重要性と実際の運用方法を理解しました。そして、トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチや、職員同士の対話が改革の進展に不可欠であること、今後、地方公共団体においても柔軟で持続可能な組織づくりが求められ、変革を恐れず挑戦し続ける姿勢が重要であると改めて認識しました。
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。





