- ホーム
- イベントカレンダー
- 新たな知と方法を生む地方創生セミナー
- 【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「新しい地域づくりへの挑戦~農村振興のために地方議会議員ができること~」
【終了レポート】令和6年度【スタンダード(平日半日型)】新たな知と方法を生む地方創生セミナー「新しい地域づくりへの挑戦~農村振興のために地方議会議員ができること~」
新たな知と方法を生む地方創生セミナー 終了レポート
2025年04月17日
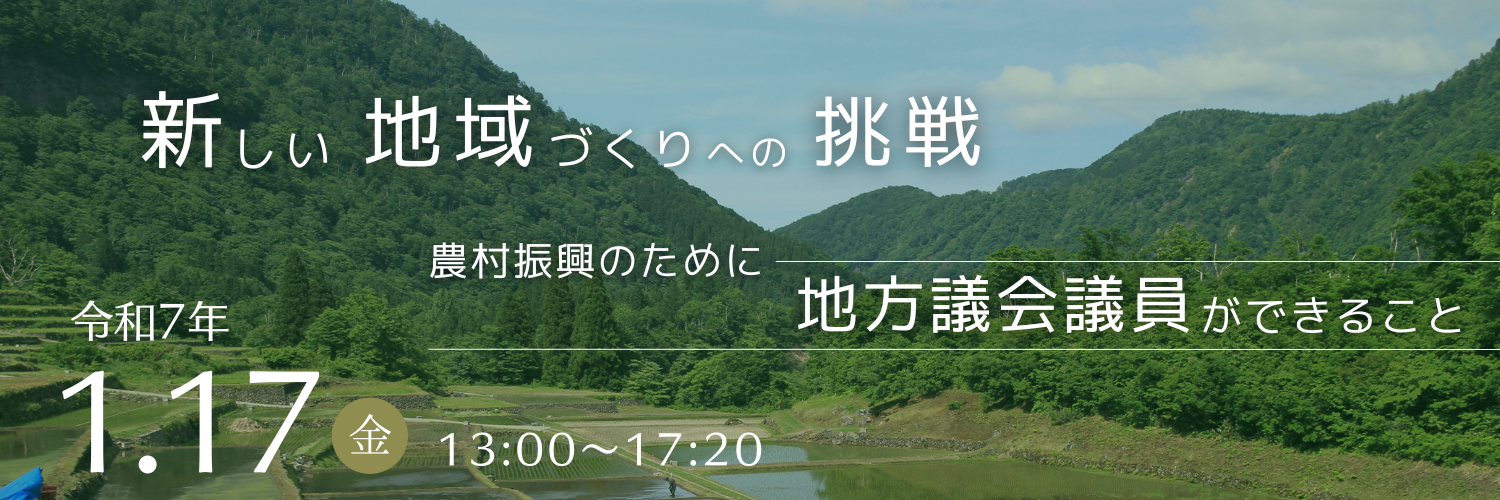
はじめに
令和6年度新たな知と方法を生む地方創生セミナー「新しい地域づくりへの挑戦~農村振興のために地方議会議員ができること~」を、2025年1月17日(金)に開催しました。地方公共団体職員、地方議会議員など現地会場60名の参加がありました。
今回のテーマ
現在、農村の持つ価値や魅力により移住に注目が集まっていますが、農村部の過疎化・高齢化に歯止めがかかっていないことも事実です。当セミナーは、地域資源の有効な活かし方や農村振興に必要な施策、地方議会議員が果たすべき役割について考え学ぶことを目的として開催しました。
講義
【主任講師】明治大学 農学部 教授 小田切 徳美 氏
農学博士。東京大学農学部卒業。同大学院博士課程単位取得退学。高崎経済大学経済学部助教授、東京大学大学院助教授等を経て、2006年より明治大学農学部教授。 明治大学農山村政策研究所代表。2021年、明治大学大学院農学研究科長。過疎問題懇談会座長(総務省)、移住・二地域居住等促進専門委員会座長(国交省)、農村RMO推進研究会座長(農水省)等を兼任。著書に『にぎやかな過疎をつくる』(農文協、近刊)、『新しい農村をつくる』(編著、岩波書店)など多数。
【講義① 】農村における「地域づくり」への挑戦(小田切氏)
日本の地方において、過疎化と高齢化が進行し、首都圏への一極集中が問題となっていますが、世界的にみると大都市集中は必ずしも常識ではないという認識のもと、地域づくりについての講義が行われました。
地域づくりとは、限られた人口でどのように幸せを育むかという視点から捉えられ、人口減少問題への適応策と位置付けられます。地域づくりに必要な3要素は人材・コミュニティ・仕事であり、これらが相互に好循環を生むことが求められます。
また、地域運営組織の役割についても触れられ、コミュニティ創生においては、守りの自治である集落と攻めの自治である地域運営組織が互いに補完し合う必要があると述べられました。
さらに、興味深い人や場所、場面の創出による地域づくりから、田園回帰や関係人口はまだら状に発生していて、地方圏や農村同士の格差「むら・むら格差」が生じており、この格差を埋めることが新たな地域の課題となっています。この課題解決のカギは人材創生であり、地域への当事者意識を醸成することが不可欠です。
最後には、多様な人材が集まる「にぎやかな過疎」の事例についても触れられ、移住者や関係人口を引き寄せる重要性を述べられました。
【特別講師】新潟県津南町 町長 桑原 悠 氏
新潟県津南町出身。早稲田大学社会科学部卒業後、東京大学公共政策大学院在学時、長野県北部地震を機に、津南町議会議員選挙に出馬し、初当選。31歳当時全国最年少で第6代津南町長に就任。(現在2期目)。国土審議会推進部会、男女共同参画会議、新しい地域経済・生活環境創生会議の委員なども歴任。
【講義②】ゆき みず だいち つなんまち 人口の成長戦略(桑原氏)
はじめに、桑原氏が生まれ育った津南町の概要と豊富な農産資源についてご紹介いただきました。続いて、人口減少・高齢化時代における成長戦略について数十年後の津南町の人口推移に触れながらお話いただきました。
さらに、人口減少の負のスパイラルを止めるための施策として、移住定住施策に関する取組や地域の若者たちが活躍できる場の創出について津南町の事例を交えながらお話いただきました。津南町で実施している移住定住施策の一つの"おてつたび"は地域外から訪れる働き手に対して、報酬や宿泊場所などを提供することで業務を手伝ってもらうもので、地域を知ってもらう機会の創出にも繋がっています。
【特別講師】総務省 地域自立応援課 地域振興室長 近藤 寿喜 氏
【講義③ 】地域力創造施策の活用可能性(近藤氏)
はじめに、総務省地域力政策グループの政策体系についてご説明いただきました。
次に、地方への人の流れの創出という観点から、地域おこし協力隊、地域活性化起業人、子ども農村漁村交流推進事業に関する施策についてお話いただきました。また、地域のくらしを守るという観点からは地域運営組織(RMO)と過疎対策について触れられ、農村振興への活用の可能性について述べられました。
トークセッション
小田切氏進行のもと、今回の講師を務めていただいた3名によるトークセッションを行いました。
はじめに、地域づくりにおける関係人口や地域運営組織(RMO)の重要性について補足されました。特に、関係人口は地域再編の可能性を広げる役割を担っているため、その意味を正しく理解することが大切であり、地域の内発的発展を手伝う貢献意識のある人とどう連携するかがこれからの課題となります。課題解決のために、行政としては地域が主体となる活動を促す取組に予算をつけるべきではないかと論じました。
また、外の人と内の人を繋ぐチーミングの必要性についても議論され、地域づくりが正しく行われているか外から概観する存在が重要だという意見が出ました。地域おこし協力隊や地域活性化起業人を上手く活用して地域に足りないものを補完し、ミスマッチが起こらないようマッチング強化に力を入れる必要性についても触れられました。
セミナーを終えて
本セミナーは、過疎化と高齢化が進む日本の地方における地域づくりの重要性を再認識させるものでした。人材創生の必要性や、多様な人材が地域に集まる「にぎやかな過疎」の事例は、地域の魅力を高めるための新たな視点を提供しており、今後の地域づくりにおいて大いに参考になると感じました。
連絡先
セミナー統括課
TEL:03-5202-6134
FAX:03-5202-0755
E-mail:seminar(at)jcrd.jp ※メールアドレスの(at)は@に変更ください。





